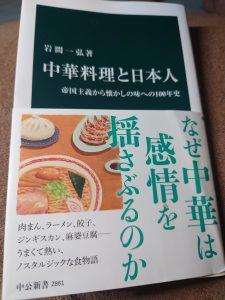「あの戦争」は何だったのか 辻田真佐憲著
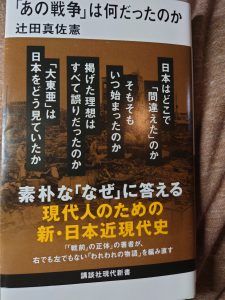
2025年8月発行
「あの戦争」と聞いて、多くの人がまず思い浮かべるのは、1945年8月15日に終結した太平洋戦争でしょう。しかし、この戦争をいつから始まったと定義するかは、単純な問題ではありません。「あの戦争」の始まりを、1941年12月8日の開戦とするのか、それとも満州事変から始まる「15年戦争」として捉えるのか。その捉え方の違いは、戦争のあり方やその性質自体にも議論を巻き起こします。
本書は、戦後80年を目前に、こうした問いかけに挑んだ一冊です。
著者は、戦争を俯瞰する視点として、ペリーの黒船来航まで遡る大胆な筋立てで議論を始めます。この視点は、極東国際軍事裁判で石原莞爾が「日本の平和を破り、近代国際社会の混乱に引き入れた張本人はペリーだ」と述べた論点にも通じます。この考え方は、後に林房雄が『大東亜戦争肯定論』でも展開したことで知られています。
なぜ日本は悲劇的な敗戦に至ったのか、別の選択肢はなかったのか。本書では、日本の海外進出を不可避とする見方がある一方で、石橋湛山の小日本主義が紹介されています。しかし、第一次世界大戦以降、戦争が国家総力戦の様相を呈すると、国力増強とそのための海外権益拡大は必須の目的となりました。そうした状況の中、日本の国家運営は場当たり的な判断の連続で、状況をさらに悪化させていったと著者は指摘します。
では、戦争へと向かう日本に大義や正義はなかったのでしょうか。戦中に掲げられた大東亜共栄圏に現実味はあったのか。本書は「八紘一宇」の解説を通して、その大義を考察します。
また、著者は実際に大東亜の地を訪れ、各国が「あの戦争」をどのように記憶しているかを記録しています。多くの国で資料館が建てられ、悲惨な記録と共に、国家の物語や政府のプロパガンダともとれる表現が展示されている現実が述べられています。
本書の結びは、「あの戦争はいつ終わるのか」という問いかけです。それは、日本が歴史としてどのように位置づけ、記憶すべきかという問いでもあります。極端な肯定も否定もなく、歴史として客観的に位置づけられるのはいつか、どうすればそれが可能になるのか。本書はそう問いかけて締めくくられています。
私は、本書の題名から軍事的な詳細が深く掘り下げられていると期待しましたが、その厚みはあまり感じられませんでした。そもそも、「あの戦争」は、特定の誰かが意図し、計画的に始めた戦争ではありません。歴史の局面ごとの指導者の判断と実行によって進んだ戦争です。ヒトラーが緻密な計画をもって始めたヨーロッパ大戦のような、グランドデザインされた戦争ではないからこそ、その実態は曖昧だと言えます。より正確に言えば、場当たり的な決定を繰り返した結果、破綻に至った戦争なのです。
私が常々考えているのは、この戦争の重大な局面は上海事変にあるということです。この認識が深まれば、戦争全体の見方が変わると考えています。
上海事変は、盧溝橋事件の飛び火で起こった大規模な戦闘です。発端は偶発的とも、どちらかの挑発とも言われ、はっきりしていません。しかし当時、上海に駐屯していた日本の海軍陸戦隊が約5,000人だったのに対し、国民党軍は日本租界を包囲する形で陣地を構築し、ナチスドイツの指導を受けた精鋭50,000人が攻撃を仕掛けてきました。この時点では、中国側の準備は周到で戦意も旺盛であり、日本は防戦一方でした。
戦闘が激化すると、日本は危機感を強め、最終的に20万人を超える陸軍を派遣しました。中国側も逐次兵力を増強し、50万の大軍を投入して大激戦となりました。しかし、日本軍が杭州湾に上陸し、後方から包囲する戦術をとると、中国側の防衛線は崩れ、南京まで後退することになります。
この事実だけを見ても、一般的な認識と事実にずれがあると考えます。たとえ日本租界への攻撃だったとしても、先に上海を攻撃したのは中国軍です。日本軍は防御戦闘から攻勢に転じた流れでした。この時点で、日本は戦争を継続するか止めるかの決定権を持っていなかったとも言えます。したがって、日中戦争を単なる日本の侵略戦争だと断ずることはできないのではないでしょうか。