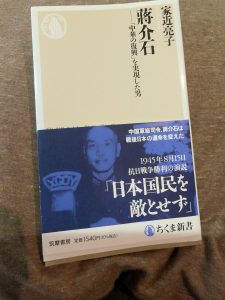1000円の壁に

現在、「ラーメン1000円の壁」が話題になっていますが、この問題を何十年も前に乗り越えていたのが永福町大勝軒です。正確な時期は定かではありませんが、40年ほど前から、従業員を月収50万円で募集し、ラーメンはすでに1000円を超えていました。
当時、私は「たんたん亭」に勤めており、月給は30万円、ラーメン一杯は500円以下でした。その頃のたんたん亭も比較的強気の価格設定でしたが、永福町大勝軒の価格には驚愕しました。「量は多いが、あの値段ならラーメン2杯分の価格だ」「従業員もあの賃金をもらうなら、相当な重労働が課せられているに違いない」といった先入観で見ていました。
しかし、私自身が経営者となり、従業員を雇ってラーメンを売る立場になって初めて、永福町大勝軒の社長の先見性に脱帽しました。社長は、現在のラーメン業界が抱える課題をすでに乗り越えておられたのです。
現在、「1000円の壁」を考える上で忘れてはならないのは、消費税10%です。例えば、「かづ屋」の支那ソバは1000円ですが、これは消費税込みの価格です。
消費税は当初、「お客様から一時的にお預かりしている税金」という認識が一般的でした。しかし、現在では「事業者への第二の事業税」的な位置づけであるとも言われています。詳細な定義はさておき、我々が値付けをする際に、この税負担を忘れてはならない重要な要素であることに変わりはありません。
市場において価格を決める大きな要因は、需要と供給のバランスです。ラーメン屋において常に行列ができている店は、需要に対して供給が追いついていないことを示しています。当然、市場の機能からすれば価格が上昇しても良いはずですが、ラーメンの価格設定は経営者の判断に委ねられています。
ラーメンの場合、規格品が大量に流通するわけではありません。その店独自の味を追求すれば、市場で唯一無二の商品として、価格が高騰してもおかしくはありません。とはいえ、ラーメンは特殊な商品であるためか、市場メカニズムがそのままでは機能しにくい側面があるようです。
ラーメン業界には夢もありますが、現実には「ブラック」な側面も指摘されています。独立開業には大きなリスクが伴うため、なおさら、経営者はしっかりとした収入を確保しなくてはなりません。適切な値付けは、業界の健全化と持続可能性のために極めて重要です。