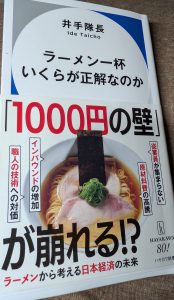蒋介石 「中華の復興」を実現した男
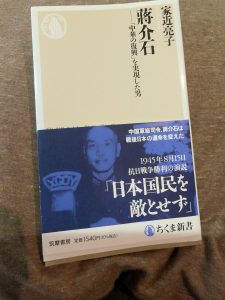
2025年8月10日発行 家近亮子著
「以徳報怨」とは、「徳をもって怨みに報いる」という意味で、1945年の第二次世界大戦終了時に、中国の蒋介石(しょうかいせき)が日本に対して述べた言葉です。
清朝崩壊後の辛亥革命に始まり、国内分裂、共産主義勢力との戦い、さらに抗日戦争と、蒋介石の生涯は未曾有の混乱と難局が連続しました。各国との連携による国際的地位の確立、対日戦勝利、そして国共内戦の敗北を経て、台湾への中華民国政府移転に至るまで、まさに途方もない試練の連続だったといえます。
日中戦争の交戦相手であった日本に対し、彼は冒頭の言葉に表される恩情を示し、この心情は戦後の日本社会に広く伝わりました。これには、彼の東洋的教養に溢れた人格が色濃く反映されています。
日本への留学や軍務経験、そして強力な敵として対峙した過去は、彼にとって日本に対して強い感慨を抱かせたことでしょう。
そんな蒋介石の生涯における大きな転機、また世界史にとっての重要な局面となったのが西安事件(1936年)です。共産勢力の殲滅まであと一歩という状況で、張学良(ちょうがくりょう)の裏切りにより監禁され、共産党との連携を迫られました。これにより、第二次国共合作を強いられ、抗日へと舵を切ることになります。
あの時点で共産党が殲滅されていれば、歴史は大きく変わり、当然ながら日中関係も異なった推移をしたでしょう。
ここで疑問となるのが、蒋介石の共産主義への理解と否定の論拠です。当時、共産主義は社会変革の重要な理論として多様に取り入れられていました。彼にとって、それはソビエト・ロシアに対する警戒感から来るものだったのでしょうか。あるいは、中華の古典的教養からの否定、共産主義そのものへの批判、または社会主義を将来的に見据えていた上での否定だったのか。このあたりの思想的背景については、論じられるべき重要な論点です。
次の大きな転機は、盧溝橋事件(1937年)から日中戦争(しなじへん)への局面です。
日中間の偶発的な軍事衝突から、様々な成り行きを経て大戦争へと発展しました。国民党と日本軍の間の事件とされていますが、共産軍も絡んだ謀略説も存在します。ただ確かなのは、国民党も日本も当初は全面的な戦闘を望んでいなかったということです。
停戦の試みもなされましたが、完全に遂行されることはありませんでした。この局面から事態が大きく動いたのは、上海での戦闘開始です。そもそも上海では、国民党は数年前からナチス・ドイツの協力のもとに、日本の租界を包囲する要塞を構築していました。蒋介石は、日本に対して勝利できるのは上海であると踏んでいたようで、この時点・場所では中国側の戦意が旺盛だったようです。
しかし、国民党は上海で敗れ、南京も陥落しました。首都を重慶に移し、日中間の長く苦しい戦いが続くことになります。
この局面での様々な判断こそが、蒋介石と中国、そして日本の歴史的な決定となっていったのです。