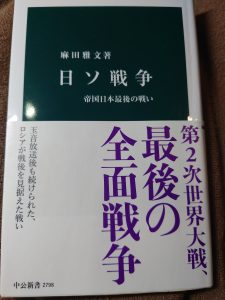帝国陸軍ーデモクラシーとの相剋
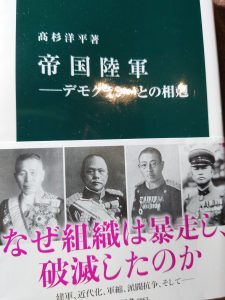
高杉洋平 著 2025年発行
明治の日本陸軍創設から太平洋戦争によるその消滅まで。副題にデモクラシーとの相克とあるように政治との関わりとのなかでその存在はどのように変化してまた如何なる理由で滅んで行ったのか。
明治政府は、かつての幕府のような強力な権力を持つ存在の出現を避けるため、軍事と政治を分離しました。この考えに基づき、日本陸軍は統帥権の独立という特殊な制度の下で成立します。これは、軍が政府の干渉を受けずに独自の軍事方針を決定し、統帥権が天皇に直属するというものです。しかし、現実には軍事予算は国家予算の一部であり、軍の意向だけで全てが決まるわけではありませんでした。
第一次世界大戦を経て、軍事技術が飛躍的に進歩しました。航空機や戦車といった新兵器の出現により、戦争は莫大な予算を必要とする国家総力戦へと変化し、軍事と政治の結びつきはより一層深まります。
一方、国内では民主主義の覚醒し大正デモクラシーと呼ばれる時を迎え、政党による議会政治が主流となりました。また、世界的な平和主義の高まりと相まって、反軍国主義的な風潮が強まり、軍人にとって生きづらい時代となっていきました。
日清・日露戦争の結果、日本は大陸に勢力圏を持つことになり図らずも島国ながら大陸国家の特質をもち、大陸の諸勢力との緊張関係が生まれます。この状況を打開しよう、謀略的な手段を用いて満州事変を起こし満州全土を勢力下にします。しかしこれは軍事的な成功を収めましたが、中国国民党政府との対立を深めます。
その後、盧溝橋事件という偶発的な衝突をきっかけに、日中戦争へと発展します。この戦争は当初、満州事変のような計画的なものではなく日本は限定的な軍事行動で収める目論見でありましたが、事態収拾の見通しが立たないまま拡大していきました。日本政府と軍部は国民党政府の交戦意思を見誤り、和平の機会を失っていきます。
日中戦争の遂行には国家総力戦が必要となり、戦争目的も当初はなかった大東亜共栄圏の確立や「アジア解放」といった大義名分が掲げられるようになります。これが太平洋戦争へとつながり、日本は敗戦を迎え、帝国陸軍はその歴史に幕を閉じました。
この一冊は、帝国陸軍が持っていた特質と、時代の変化に対応できなかった問題点を端的に示している良書です。
クラウゼヴィッツの「戦争は他の手段をもってする政治の延長である」という名言は、軍事が政治に内包されるものであることを示しています。これは、帝国陸軍の興亡からも明らかです。
現代の国家安全保障を考える上でも、この教訓は非常に重要です。日本では依然として反軍国主義的な考え方が根強いですが、軍事を抜きにした安全保障は成り立ちません。平和主義は大切ですが、それを実現するためには、外交においても有効なカードとなる軍事力を適切に保持・運用することが不可欠であると言えるでしょう。