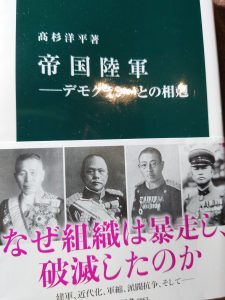麺線を揃える

ラーメンの麺線(めんせん)、つまり麺が美しく整っている状態を重視する方は少なくありません。私の作るラーメンもその点において評価をいただいており、また「かづ屋」の出身者達も同様に皆様からと美しい麺線と認めていただいています。
正直なところ、いつからこのようなフォルムのラーメンを作るようになったのか、はっきりとは断定できません。むしろ、時間をかけて少しずつ今の形になってきたというのが実情です。
私が「たんたん亭」で教わった麺上げは、平ざるを使う点は今と同じです。しかし、麺を釜からすくって丼に移すやり方は、当時と現在では少し異なっていました。以前は、平ざるにすくった麺を手首の返しでざるの上で数回クルクルと回しながら湯を切り、それから丼に移していました。
現在、私のやり方は異なります。菜箸で釜の麺をすくう際に、できるだけ真っ直ぐ揃えるように持ち上げます。それを、できるだけ崩さないようにざるの上に揃えて置きます。そして、湯切りを数回行った後、ざるに乗った麺の形状を崩さずに丼へ移すのです。
なぜこのような手法になったのか、特別な意識があったわけではありません。しかし、記憶にあるのは、かつて渋谷のラーメンスクエア「麺道場」の中にあったラーメン屋で食べたラーメンの麺線が非常に整っていたことに感動し、「自分もこれができないだろうか」と試行錯誤を重ねた結果だということです。
麺線を揃えることへの執着はそこまで強くなかったので、特別なトレーニングやそのための試作は行いませんでした。あくまで通常の営業の中で、注文をこなしながらの試行錯誤でした。そうした繰り返しの中で、たまに偶然きれいに整うことがあり、その時の所作はどうだったのか自身で確認し、麺線が整うメカニズムを後付けで確立していったのです。
この麺上げの技術が確立されたのは、おそらく平成5年(1993年)頃だったと思います。だいたいラーメン職人になって10年目といったところでしょうか。
しかし、せっかく確立したこの技術がうまくいかなくなる展開もありました。それは、自家製麺への移行です。平成12年(2000年)に店舗拡張と同時に自家製麺を始めましたが、そこで完成した麺は「つるつる」とした食感でした。舌触りが良くて良好かと思われましたが、麺上げの際に菜箸で掴みづらくなってしまったのです。
さらに、想定した麺の重量を取ろうとすると、麺の長さも長くなり、盛り付けにくくなりました。また、今まで仕入れていた製麺所の麺は、若干のウェーブがあり、菜箸に絡みやすかったようです。その後、麺を手揉みにしてウェーブを付けて麺上げを試したりもしましたが、「つるつる麺」の方がお客様の評判が良く、結局ストレートに戻しました。
そうしたつまずきもありましたが、麺を掴みやすくするために菜箸を選び直したり、さらに箸の表面をギザギザに加工したりと工夫を重ねました。当然ながら、指使いや腕使いの修練も重ねました。
こうして確立された、麺線を揃える麺上げは、「かづ屋」で働く従業員が皆、習得に励んでいます。これまでの従業員の中には、私より上手になった者もいます。
しかし、そんな皆に指導するにあたって、私の方針は「そこまで麺線にこだわらなくても良い」というものです。
ラーメンの美味しさにおいて、麺線が最上位のポイントではないからです。ラーメン作りのあらゆる要点が押さえられ、最終的に出来上がりの結果が美しく整っていれば良いと考えます。例えば、味がしょっぱかったり、麺が伸びていたり、スープがぬるかったりするようなラーメンであれば、整った麺線があっても滑稽です。
さらに、製作工程においてことさら麺線を揃える作業に固執して時間がかかりすぎてもいけません。あくまでも調理は素早く、スムーズに、無駄なく。そんな作業の結果として出来上がった美しさにこそ価値があると言えるでしょう。