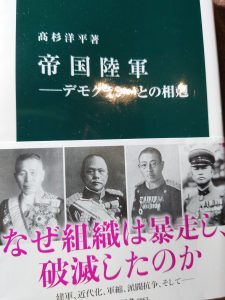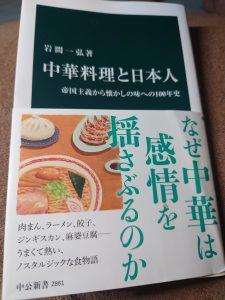麻田雅文著 日ソ戦争 帝国日本最後の戦い
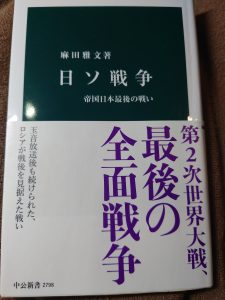
2024年4月発行
日ソ戦争とは、第二次世界大戦および太平洋戦争の最終局面である1945年8月8日に開戦し、9月初頭まで続いた戦争です。わずか1ヶ月ほどの短期間でしたが、その被害と、その後の国際情勢に与えた影響は甚大でした。しかし、この戦争の実態はあまり知られていません。本書では、その全容を新書のサイズでまとめています。
まず、本書ではなぜ、そしてどのようにして戦端が開かれたかが述べられています。
太平洋戦争の終盤、アメリカは自国の損害を最小限に抑え、戦争を早期に終結させる方法を模索し始めました。その中でトルーマン大統領が進めたのが、ソ連の極東における対日参戦でした。早期の日本打倒には核兵器の開発も進められており、それだけで目標は達成できるという考えも一部にはありましたが、大勢としてはソ連参戦も同時に行うべきだというものでした。
当時、日ソ間には日ソ中立条約がありましたが、この条約は両国にとって、いざとなればいつでも破棄できるものと見なされていました。従来から日ソ間には潜在的な敵対関係が存在しており、状況さえ許せば、それを解決するための行動に出ることに両国とも迷いはありませんでした。
アメリカからの参戦要求に対し、ソ連は独ソ戦終了後、準備ができ次第開戦すると回答しており、それは8月10日頃と予測されていました。しかし、日本政府はそれを知らず、米英との講和の仲介をソ連に依頼していました。その回答を受けに外務省へ赴いた時点で、日本側はソ連から宣戦布告の通告書を手渡されることになります。
開戦は周到に準備されており、圧倒的な戦力のソ連軍によって満州全土は蹂躙されました。戦闘は千島列島や樺太にもおよび、一部では激しい戦闘が行われました。
日本政府はポツダム宣言を受諾し、連合国との戦闘は終結に向かいますが、ソ連軍の指揮系統に米軍からの指示は直接届かず、戦闘終了には手間取り、無用な犠牲者が増えました。さらに、ソ連は北海道占領を目論みましたが、これはアメリカが許容するところではありませんでした。
このように、日ソの全面戦争は1ヶ月に満たない期間でしたが、日本側の死傷者は軍民合わせて30万人にものぼり、さらに60万人以上のシベリア抑留者を出しました。これは甚大な被害をもたらした戦争でした。
この本の最後は「この戦争が、不信感を基調とした日ロ関係の基調となった」と締められています。
読了後、改めて考えてみると、この残念な事態の成り行きが、未解決の諸問題の種を植え付けた戦争であったことがわかります。
なぜルーズベルトはスターリン率いるソ連を信用したのでしょうか。その後の展開を予想できなかったのでしょうか。対日戦は本土決戦目前で日本の敗北は揺るがない状況でしたが、アメリカ国民の犠牲を抑えるためにも、できるだけ早く日本を打倒したいという思いがありました。しかし、ソ連参戦の結果生まれた極東の緊張関係は、さらなる紛争の種となりました。朝鮮戦争でアメリカ軍はどれだけの犠牲を強いられたことか。さらに血を流しても問題は解決されず、今もなお緊張関係は続いています。
現在のウクライナ戦争を目の当たりにすると、ロシアは社会主義国家ではなくなり、世界革命の普及という理念もなくなったとしても、自国の利益のためには武力行使をためらわないという現実があります。そのような国家を隣国に持つ日本の現実は、重いと言わざるを得ません。