塩対応の研究

飲食業は広い意味でのサービス業ですが、時折信じられないほどの「塩対応」に遭遇することがあります。私自身が飲食業に携わっているため、働く人の気持ちは少なからず理解しています。客として、どのような態度が「嫌われるか」はだいたい把握していますし、働く方には気持ちよく仕事をしてほしいという思いもあります。そんなところで私は基本的に敬語を使います。年配になると若者に対して敬語を使わない人もいますが、敬語は年齢や立場に関係なく、人との適切な距離感をもって使われるべきだと考えているからです。いつも敬語を使っているにもかかわらず、まれに塩対応に遭遇するとがっかりします。
先日も、あるスパイスカレーの店で、嫌悪感を露わにしたような接客をされました。カウンターだけの小さな店で、店主がワンオペ(一人での営業)で経営されていました。何が店主の気に障ったのか考えながらカレーをいただきましたが、美味しいカレーでも「また来たい」とは思えませんでした。
しかし、これは他人事ではありません。翻って自分自身の過去を振り返ると、かつて私もワンオペで営業していた時間帯があり、その時にお客様に塩対応をしていなかったかと言えば、そうではありません。思い当たる節があり、心当たりのある対応の後には後悔の念に駆られた記憶もあります。
そんな過去の経験から、塩対応の原因について考えてみました。
私の塩対応を思い返すと、その根底には「技量不足」がありました。オープンキッチンの営業では、常に接客と調理を同時に行う必要があります。その場合、意識を異なる方向に同時に向ける必要がありますが、調理技術が低いと、そちらに意識を完全に持っていかれてしまい、接客が疎かになってしまうのです。
調理技術を磨いて独立開業したつもりでも、常に調理に集中できるわけではありません。調理を段取り良く進めたいと思っていても、イレギュラーな状況は起こりえます。特にオープンキッチンであれば、お客様と接しているため、いつ何時でも様々な要求があります。調理が活況な時に、新しいお客様の来店が重なることもあります。
特に開業して間もない頃は、新しいお客様ばかりです。店の方針があったとしても、まだ十分に周知されていません。
雇われていた頃のお店であれば、馴染みのお客様は店の「お約束」もご存知です。私が勤めていた「たんたん亭」もそのような店で、お客様からの温かい視線に包まれていました。
しかし、独立開業をすれば、自分の店であるにもかかわらず馴染みのないお客様ばかりになります。いわば、「ホーム」にいるつもりが「アウェイ」で試合をしているようなものです。
いくら調理技術を磨いたとしても、それ以外に「接客術」がなければ、その技術を活かせない。もしくは、半端な調理技術ではオープンキッチンでは通用しない。それが現実です。
さらに、店が忙しくなれば、注文の集中や複雑化も起きてきます。同じような注文が同じペースで来てはくれません。そこで手順を組み立てて調理を進めますが、自分のミスも起こります。また、思い通りの味が出ない場合もあります。そうなると、自分自身に対して腹が立つものです。
そうなると、とんでもない形相でオープンキッチンでお客様に晒されることになります。そして、それがお客様に「塩対応」だと誤解されてしまうのです。
塩対応の裏には、「ワンオペ」「調理技術と接客の同時遂行」「アウェイでの営業」「自分のミスへの苛立ち」など、複合的な要因が絡み合っています。

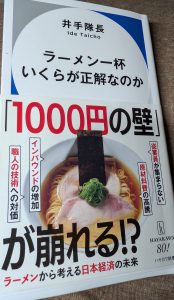
店側の塩対応、ほんと嫌ですね。
でも店側からすれば少なからずア◯な客の対応もしているはずなので接客自体が嫌いで我慢している店主さんもいるでしょう。
大盛り出来ないメニューで大盛り券買った事あるし、店の掲示ミスで食券が分からなかった事もあるし…
お互い様なんでしょうね。
自分は塩対応されるのが嫌だから行かない選択しか無いです。
客は嫌なら文句言わずに他の店に行けば良いと思います。
この問題は奥深いところがあります、引き続き掘り下げるつもりです。