渡来人とは誰か 高田寛太著
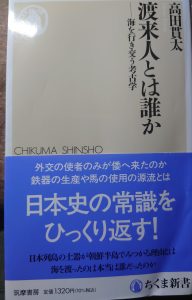
2025年8月発行 海を行き交う考古学
日本の古代史を考察する場合、文献史と考古学、両面からのアプローチがなされています。文献史の拠り所は、中国の歴史書と日本の『古事記』『日本書紀』です。
しかし、中国の史書における日本列島、あるいは倭国に関する記述は、古代史の全域をカバーしているわけではなく、空白の4世紀と呼ばれる期間も存在します。一方、『古事記』『日本書紀』に歴史書としてどこまで信頼性を持たせるかについては疑問が残ります。過去の国粋主義への反省からか、その内容を史実として扱うかどうかについての言及には歯切れの悪さが見受けられます。
このような状況において、古代史における考古学の比重は一層重くなっていると言えます。
著者は考古学が専門で、多くの古墳の発掘を手がけられています。特に韓国南部にある倭人の古墳からの多くの発見は、この地域における空白の4世紀の実相に迫るものです。
この時代の歴史学的課題の多くは、朝鮮半島南部における倭人の存在です。かつては、朝鮮半島南部に倭人の勢力範囲があり、「任那日本府」などと称されていました。この認識に対する反発が韓国や日本国内にあり、否定的な研究がなされてきました。民族的感情や日本の近代に対する過剰な反省など、いくらかバイアスのかかった考えとも言えますが、なによりも、古代においても日本の「植民地」が朝鮮半島にあるという認識は都合が悪いのでしょう。
近年に、朝鮮半島の南西部では日本式の古墳が多く発見され、この地域での倭人の存在が再び注目されています。この著者は、そうした研究の最前線に立ち、新たな論説を展開しています。その説は、この時期の日本列島と朝鮮半島との交流が、従来考えられていた以上に密接であったという実相を解明するものです。
日本に渡ってきた渡来人が倭国内で重要な役割を果たしていたことは、先行研究でも述べられています。ここでは、その逆方向、すなわち日本列島から朝鮮半島への渡航者を追った研究がなされています。日本式古墳からの出土品は、そこに葬られた人物の地位の高さを窺わせ、その渡航意図について想像が掻き立てられます。
しかし、著者の探求、あるいは論述には踏み込みの緩さがあるのではないでしょうか。当時においても、歴史上のあらゆる時点においても、人の行き来は単なる物見遊山ではなく、生きるための行為であったはずです。そこには、勢力争いや生存競争といった厳しさが伴い、共同の敵や脅威から協力して対抗すべき協力関係や、反目もあったでしょう。
著者の記述は、「朝鮮半島の人々と倭人が混在する生活圏があった」と、ややほのぼのとした雰囲気を醸し出しています。しかし、倭人が半島南部に相当数居住していた事実があるならば、そこには倭人国家の力、すなわち勢力範囲が存在したはずであり、それを無視はできません。
近代以降の尺度で考えると、事実は見えてきません。日本列島の倭人国家が朝鮮半島の一部に勢力圏をもっていたとしても、それは近代における植民地とは異なると思います。また、朝鮮半島に鼎立した国家にしても、近代における国民国家や民族国家とは色合いが違うでしょう。半島の国々の民族構成も、今の国民とは異なっていたはずです。
各国は、狩猟系のツングース族、農耕系の朝鮮族や漢族、また倭人など、多様な人々で構成されていました。また、日本列島にしても、倭人と渡来系の朝鮮族や漢族などがおり、それらがまだしっかりと混合されきっておらず、国が成立する以前であり、柔軟な視線が必要です。今後の研究に期待します。

