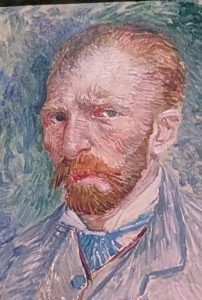論争 大坂の陣 笠谷和比古著
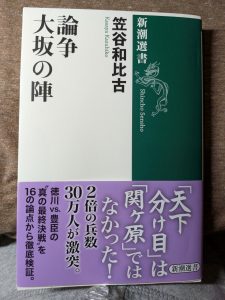
2025年10月発行
日本史の中でも「大坂の陣」は、これまで長きにわたって語られてきた分野です。それにも関わらず、いまだに新たな見解が出てくるものです。
かつては「立川文庫」的な物語、すなわち、「狡猾な古狸」徳川家康が弱体化した豊臣家を滅ぼそうと策謀を巡らし、それに対抗する真田十勇士という構図でした。私も子供の頃には、こうした物語に血湧き肉躍るような興奮を覚えたものです。
しかし、この本書では、新たな資料の読み込みにより、従来とは異なる像を浮き彫りにしています。その為、歴史の新刊本にはいつも注目しています。
まず、豊臣家を滅ぼそうとする家康の「本心」は、関ヶ原の合戦後、当初はそこまで強い意思はなかったのではないか、という見方です。関ヶ原以後、家康はただちに徳川幕府を成立させ、豊臣家はわずか65万石の一大名になったという印象がありますが、実際は徳川と豊臣の支配領域は西日本と東日本とはっきり分かれており、「二重公儀制」といった実態ではなかったかと論じられています。
にもかかわらず、家康が自ら亡き後に残る豊臣家の存在は天下を揺るがす脅威となると考え、生きているうちに解決しておこうと決断したわけです。
そうして始まった大坂の陣は、関ヶ原以上、さらに世界史的にみても未曾有の戦闘になったようです。
その激戦となった戦闘内容も、通説とは異なった論述があります。
一つは、大坂の陣の名高い真田信繁(幸村)による攻撃、およびそれによる家康本陣の潰走は、実は毛利勝永の部隊によるのが真実だというものです。これまでの真田家と信繁の高名から、憶測的に、また不確かな伝聞による一次史料によって裏打ちされて広がったようです。しかし、直接の目撃者による一次史料や、戦闘当日の陣地状況から、家康本陣に突入したのは毛利勝永隊であると本書は結論づけています。
また、この時の毛利隊の戦闘は、「捨て身の全隊突撃」により徳川方の前衛が崩れ、その潰走する徳川方に離れず次々と第2陣に突入し、潰走する部隊の混乱がさらに第2陣を崩し潰走させました。このように「間髪入れぬ」「後を考えぬ」攻撃が、家康本陣を混乱に陥れて潰走させたようです。
いわば、織田信長が「桶狭間の戦い」において行なった「捨て身の全軍突撃」の如くであったとも表現されています。ここからはさらなる筆者の憶測ですが、家康の脳裏をよぎったのは、かつての主君であった今川義元の無念の最期であったかもしれぬと。たしかに面白い推測です。
あらゆる学問もそうですが、歴史学も例に漏れず、年々新しい研究成果が発表されています。